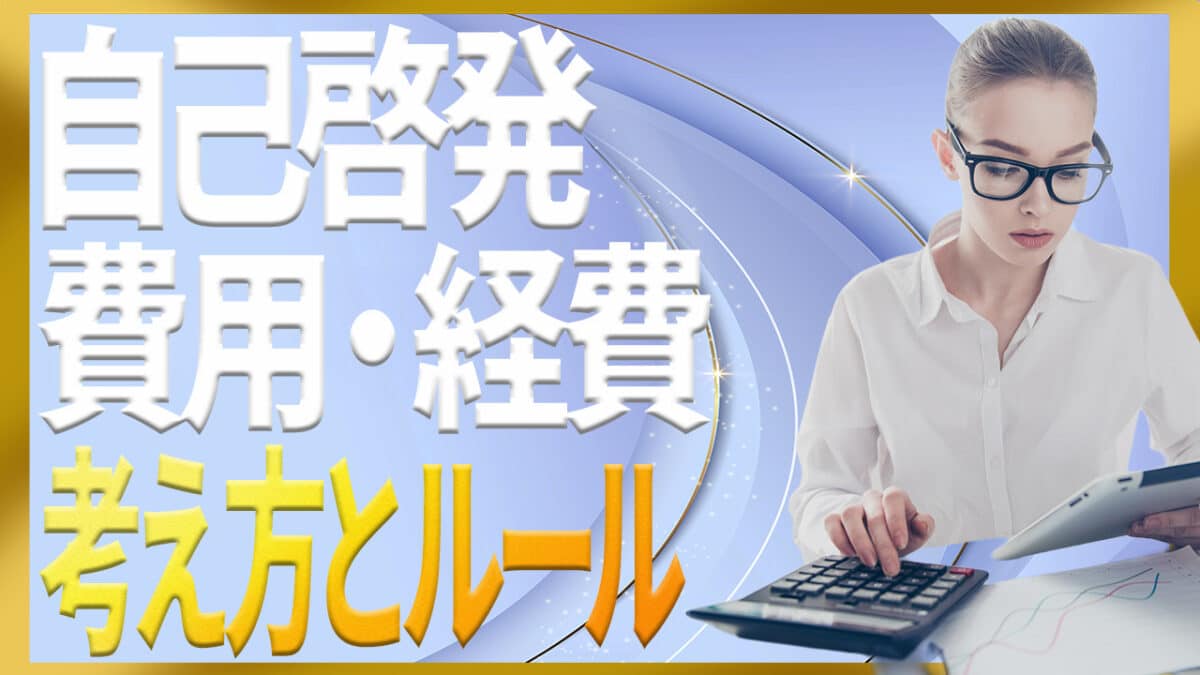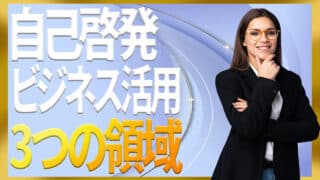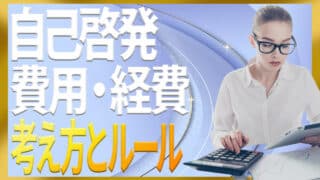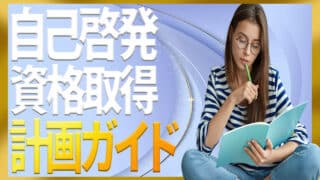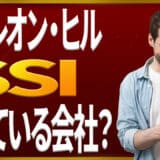自己啓発の費用と経費の考え方|会社負担と自腹のルール例
今回は自己啓発の費用と経費の扱いについて解説します。
・自己啓発の費用でお金をどこまでかければ良い?
・自己啓発は仕事に関わるなら経費になる?
こうした疑問や思いをお持ちの人はたくさんいます。
自己啓発の費用を適切に扱える人は、投資としてリターンを得ることで自己成長を重ねていきます。
しかし無駄に費用が膨らむだけの人や、節約によって成長のチャンスを逃している人も多いです。
そこで今回は自己啓発の費用の基本的な考え方について解説します。
この動画を見ると費用の考え方と、家計とメンタルを守るお金のルールが分かりますので是非最後までご覧ください。
それでは早速、自己啓発の費用をどう考えるかから見ていきましょう。
自己啓発の費用をどう考えるか
自己啓発の費用を考えるとき、最初に決めておきたいのは「これは自分にとって投資か消費なのか」という視点です。
なんとなく気分が上がるだけの出費と、具体的な行動の変化につながる投資かを区別しましょう。
そうすればお金の使い方に迷いが少なくなり、意識が変わることで取り組みの熱も変わってきます。
自己啓発の費用を全部ひとまとめに「良いもの」と見てしまうと、勢いで高額な講座に申し込んで後悔するリスクも高くなります。
先に基準を決め、その基準に照らして判断する癖をつけておきましょう。
分かりやすくするために、自己啓発の費用を「投資」「消費」「浪費」の三つに分けて考えてみます。
投資は仕事の成果や生活の質の向上など、将来のリターンがはっきりイメージできるものです。
仕事に直結する学びの選び方は、自己啓発をビジネスで活かす設計から逆算すると迷いませんし安心です。
消費は役には立つけれどなくても大きな支障はないもの、浪費は目的が曖昧で終わった後に何も残らない出費です。
自己啓発の費用でも「この講座は自分にとってどれか?」と一度立ち止まって考えるだけで、選び方は大きく変わります。
次の表はこの三つの違いを簡単にまとめたものです。
この表は自己啓発の費用を分類する目安として使ってください。
| 区分 | 目的のイメージ | 例 | 終わった後に残るもの |
|---|---|---|---|
| 投資 | 成果や収入アップに結びつけたい | 仕事に直結する資格、実務スキル講座など | スキル・実績・行動の変化 |
| 消費 | 気分転換や軽い学びとして楽しみたい | モチベーション系の本、ライトなセミナーなど | 一時的な気分の変化や軽い知識 |
| 浪費 | なんとなく不安で勢いで申し込んでしまう | 中身をよく調べず契約した高額講座など | 支出だけが残り、具体的な変化が実感しにくい |
自己啓発の費用そのものが悪いわけではなく「投資」「消費」「浪費」のバランスが崩れると苦しくなります。
自分は今どこに偏りがちかを振り返り「今は投資にあたるものだけに絞ろう」といったルールを持ちましょう。
そうすることで、心とお財布の両方を守りながら自己啓発を続けやすくなります。
実際に私も月の上限を決めずに教材を買い足した時期は、半年で支出だけが増えて行動が変わりませんでした。
そこで上限を手取りの3%に固定して毎月一つだけ実行テーマを決めるようにしました。
すると1ヶ月後には学習時間が週2時間から週5時間に増えました。
ただし上限を低くしすぎると必要な講座を先延ばしにし、成長が遅れるというデメリットもあります。
自己啓発の費用の目安と優先順位づけ
次に自己啓発の費用をいくらまで使って良いのかという目安を考えてみましょう。
一般的には手取り収入の数%を「成長のための予算」として確保する考え方があります。
例えば「手取りの3〜5%を上限にする」と決めておけば、月々の家計を圧迫せずに自己啓発の費用を確保できます。
大切なのは、他の生活費や貯金を削ってまで自己啓発を優先しないことです。
生活が不安定になると、いくら良い内容でも冷静に学びを活かしづらくなります。
具体的なイメージをつかむためにも、簡単な例を見てみましょう。
手取り25万円の人が「自己啓発の費用は月1万円まで」と決めたとします。
書籍代が3千円、オンライン講座が5千円、残り2千円は貯めておき、数ヶ月に一度少し高めのセミナーに参加、などです。
このように天井を決めると「予算を超える講座は今回は見送る」と自分を諭しやすくなります。
これであれば、勢いで高額な契約をしてしまうリスクも減ります。
私のクライアントの事務職の人は、自己啓発の費用を月1万円までと先に決めて書籍・講座・積立の比率を固定しました。
すると2週間で迷いが減り、平日でも15分だけ復習する行動がすぐに習慣化しました。
そして1ヶ月後には、学びの実行回数がゼロの日をほぼ作らずに済むようになりました。
また自己啓発の費用の優先順位を決めるときは「今の自分に一番効きそうな一つ」を選ぶ意識が大切です。
「不安だから全部まとめて変えたい」と思うと、時間もお金も足りなくなってしまいます。
まずは仕事に直結するスキル、次に生活の土台を整える知識、最後に余裕があれば趣味に近い学びと順番を決めましょう。
一度にたくさん手を出すよりも、一つの講座や本をしっかり実践する方が自己啓発の費用を無駄にせずに済みます。
迷うときは具体例を先に見て、自己啓発の仕事の例を自分の業務に置き換えると決めやすく失敗が減ります。
自己啓発の経費になるケース・ならないケース
ここからは「自己啓発の費用は経費にできるのか?」という視点を整理していきます。
個人事業主やフリーランス、会社経営者の場合、仕事に必要な学びであれば自己啓発の経費として計上できる可能性があります。
ただし「何でもかんでも経費で落ちる」というわけではありません。
税務上はあくまで「事業に必要かどうか」が問われます。
ですので、趣味に近い自己啓発の費用は認められない場合が多いと考えておいた方が安全です。
グレーな部分が多いテーマだからこそ、自分なりの基準を持って最終的な判断は専門家に相談する前提で動きましょう。
自己啓発の経費として認められやすいのは、今の仕事や事業と直接関係するスキルアップのための講座やセミナー、本などです。
例えば営業職が営業スキル講座を受講、税理士が税法改正セミナーに参加、デザイナーが専門ソフトの講座を受けるなどです。
一方で「人生哲学」「自己実現」「スピリチュアル」など、仕事との関係が弱い内容は、自己啓発の経費になりづらいです。
同じ自己啓発の費用でも、内容や仕事との距離感によって扱いが変わる点を理解しておきましょう。
次の表は、自己啓発の経費になるものならないものを、あくまで目安として整理したものです。
経費の扱いで迷うなら、自己啓発の経費の判断基準と証拠の残し方を先に押さえると安全ですので確認しましょう。
この表は経費にできそうかどうかを検討する際の参考として使ってください。
最終判断は税理士や所轄の税務署に確認しましょう。
| 区分 | なりやすい例 | なりにくい例 |
|---|---|---|
| 内容と職務の関係 | 今の職務に直結する専門講座 | 仕事と直接結びつかない一般的自己啓発 |
| 目的の書き方 | 顧客対応力向上、業務効率化など具体的な目的 | 「人生を変えたい」「意識を高めたい」など抽象的な目的 |
| 証拠となる資料 | 講座概要、領収書、メモ、実務での活用記録など | 資料がなく、ただ受講した事実だけ |
自己啓発の費用を経費にしたいと思ったときは、次に挙げる2点をチェックポイントにしてみましょう。
- 仕事との関係を一言で説明できるか
- 証拠となる資料を残せるか
曖昧な状態で経費にすると、後から指摘を受けるリスクもあります。
もし迷う場合は、自己啓発の費用として個人負担にとどめるか、事前に専門家へ相談するのが安心です。
自己啓発の通信教育が会社負担になるか自腹かの振り分け
自己啓発の費用でよく相談があるのが、通信教育や資格講座をどう扱うかというテーマです。
内容や受講目的によって、会社負担にしやすい自己啓発の通信教育と個人の自腹にすべき通信教育に分かれます。
線引きの目安を一度整理しておくと、上長や人事に相談するときも説明しやすくなります。
会社の研修と近い内容なら、自己啓発の研修の位置づけを知ると相談の筋道が立ち通りやすくなります。
次の表は通信教育・資格講座を例に、会社負担になりやすいケースと自腹になりやすいケースを並べたものです。
| 区分 | 会社負担になりやすい自己啓発の通信教育 | 自腹になりやすい自己啓発の通信教育 | チェックポイント |
|---|---|---|---|
| 資格系通信講座 | 現在の職務に必須・推奨の資格取得講座 | 将来転職を見据えた、今の職務と距離のある資格講座 | 職務との関連性を一文で説明できるか |
| 実務スキル講座 | 部署の課題解決に直結する実務講座(営業力強化、マネジメントなど) | 「いつか役に立ちそう」レベルの一般スキル講座 | 部署の目標や評価指標と結びつけられるか |
| 教養・趣味寄り講座 | ほぼ該当なし(会社ロゴでの公募講座など特例のみ) | 語学・教養・ライフハックなど趣味に近い内容 | 職務との関係を説明するのが苦しい内容かどうか |
例えば新人育成を任されているリーダーが新任マネジャー向け通信講座を受けるなら、投資の意味合いが強くなります。
一方で今の職務と直接関係のない趣味の資格や、自己実現寄りの講座であれば自分の自己啓発として自腹の方が自然です。
資格系を選ぶ前に、自己啓発の資格の選び方で費用対効果を見積もっておくと後悔しにくいですし安心です。
自己啓発の通信教育を会社に相談するときは、この内容が自部署の成果にどうつながるかを簡潔にメモにしておきましょう。
そうすれば会社負担になるケースと自腹にすべきケースの線引きを、自分でも納得しながら決めやすくなります。
自己啓発の費用を会社負担・補助にしてもらう考え方
次に会社員として働きながら、自己啓発の費用を会社負担や補助にできないかという視点を見ていきましょう。
会社によっては、資格取得や通信教育を支援する自己啓発の会社負担制度を用意しているところもあります。
制度の有無は会社で違うので、自己啓発を会社で進める前に就業規程と窓口を確認すると揉めにくいです。
制度がなくても内容やタイミングによっては、上長と相談すれば一部負担や勤務時間内受講を認められる可能性があります。
ただ「何となく良さそうだからお願いします」というのはおススメしません。
これだと相手から見てメリットが分かりにくく、断られやすくなってしまうからです。
自己啓発の費用の会社負担をお願いするときは、次に挙げるの三点を短く説明できるようにしておくことが大切です。
1,目的
2,仕事へのメリット
3,具体的な内容と金額
「新人教育の場面で説明力を高めたいので、プレゼン講座を受講したいです。受講費は〇円で、終了後は学んだ内容をチーム全体に共有し、資料テンプレートを作るつもりです」
このように自己啓発の会社負担が会社にとっても投資になることを示せれば、前向きに検討してもらえる可能性は高まります。
補助の相談では自己啓発の費用を会社負担にする理由と効果を一文で示すと、交渉がブレませんし判断も早まります。
また自己啓発の費用の会社負担については次のような線引きを意識しましょう。
「どこまでが業務としての研修で、どこからが個人の自己啓発なのか」
業務命令としての研修であれば勤務時間中に参加するのが前提です。
しかし個人の自己啓発としての参加は、勤務外や休日が条件になる場合もあります。
会社の就業規則や人事制度を一度読み「応募できる制度がないか」「個別に相談できる窓口はないか」を確認しましょう。
そして相談の際には、感情よりも事実とメリットを中心に話すことを意識しましょう。
私のクライアントで営業職の人は、申請文を「現状課題→学ぶ内容→期待する変化→共有方法」の順で一段落にまとめました。
そして成果指標を成約率の改善のように数字で入れました。
すると初回申請で承認され、翌月からは学んだ型をチームに共有する運用まで整いました。
家計とメンタルを守る自己啓発の費用管理
最後に家計とメンタルの両方を守るための、自己啓発の費用管理のコツをまとめます。
自己啓発は一度始めると「あの講座も必要かもしれない」「この教材も買っておきたい」と気持ちが膨らみやすい分野です。
気づいたらクレジットカードの請求が増え、家計が苦しくなって、かえって心の余裕を失ってしまうケースも少なくありません。
大切なのは「自己啓発のためなら何をしても良い」という考え方から距離を置くことです。
そして「生活と心の安定を守れる範囲で続けること」を自分との約束にすることです。
具体的には、自己啓発の費用を管理するための三つのルールを決めておくと良いでしょう。
一つ目は「分割払いや高額ローンは原則避ける」ことです。
支払いが長期にわたると、気持ちの負担も長く続きます。
二つ目は「一度に契約するのは一つだけ」にすることです。
複数の講座を同時進行にすると、消化しきれずに自己嫌悪につながりやすくなります。
三つ目は「次の講座は今の取り組みを一定期間続けてから決める」というルールです。
これだけでも、自己啓発の費用の暴走をかなり防ぐことができます。
もしすでに自己啓発の費用で苦しいなら「今ある教材や本の中で今日できることは何か」を探してみてください。
新しいものを足すのではなく、手元にあるものを最大限活かす方向へ意識を切り替えるイメージです。
「この本から一つだけ行動を決める」「買った講座の動画を一回見直しメモを取る」といった小さな一歩からで構いません。
自己啓発は常に何かを買い足さなければ、続けられないものではありません。
自分のペースとお金の状況を尊重しながら、長く付き合える形を探していきましょう。
実際に私も過去に同時に二つ以上の講座を契約した月は消化が追いつかず、結局どちらも中途半端になりました。
そこで「契約は一度に一つだけ」「次は4週間続けてから検討」と決めるようにしました。
すると次月以降は支出が安定し、行動の継続率も上がりました。
編集後記
自己啓発の世界に踏み込むと「もっと学ばなきゃ」「全然足りない」という気持ちが強くなり、その勢いで浪費する人がいます。
その気持ち自体は決して悪いものではありませんが、後から家計や心が追いつかなくなるなら論外です。
なぜなら、それでは「自己啓発なんてやらなければ良かった」と感じてしまいやすくなるからです。
私自身、多くの相談を聞いて感じるのは「お金のルールを決めた人ほど、学びとの付き合いが長続きしている」ということです。
もし今少し不安があるなら、今日一つだけ自分なりの上限額や優先順位を書き出してみてください。
その紙一枚がこれからのあなたへ宛てた、自己啓発の費用を守る小さな保険になります。
- 自己啓発の費用は投資と消費を分けて考える
- 自己啓発の費用は収入に合わせて上限を決める
- 自己啓発の費用は通信教育など具体例も含めて検討する