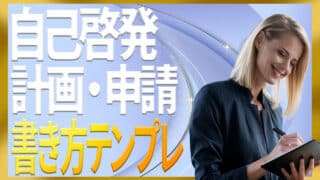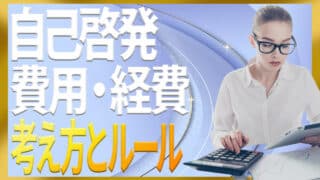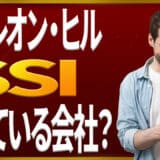自己啓発の研修内容の作り方|eラーニングとの違いと選び方のポイント
今回は自己啓発の研修内容の作成と選定方法について解説します。
・自己啓発の研修内容はどのようにすれば良いのか
・自己啓発の研修内容は全部eラーニングでもOK?
こうした疑問や思いをお持ちの担当者はたくさんいます。
自己啓発の研修内容をきちんと設計できれば、社員の成長と会社の成果の両方を支える心強い仕組みになります。
一方で現場の仕事に直結しないと「忙しいのに時間の無駄」と受講者の不満がたまり、逆効果にもなりかねません。
「集合研修とどう分ければいいのか」「どこまでをオンラインでやるべきか」が見えにくく損をしている人も多いです、
そこで今回は自己啓発の研修内容の作成と選定方法について解説します。
この動画を見ると自己啓発の研修内容の作り方、自己啓発のeラーニングとの違いが分かりますので是非最後までご覧ください。
それでは早速、自己啓発の研修内容を導入するところから見ていきましょう。
自己啓発の研修内容を考える前に整理したいこと
自己啓発の研修内容を決める前に整理しておきたいのは「研修なのか自己啓発の支援なのか」という位置づけです。
研修は会社主導で業務に必要な知識やスキルを教える場であり、基本的には受講が必須になります。
自己啓発の研修を全体設計から見直したい人は、目的と対象を一行で言語化してから進めると迷いません。
一方で自己啓発は社員本人が主体となって学ぶもので、会社はその背中を押す役割です。
自己啓発の福利厚生として制度化する場合は、対象と条件を社内に明文化すると運用がぶれません。
この二つが曖昧なまま研修内容を決めてしまうと「任意のはずが実質強制」「評価にどう反映されるのか」などの不満が生まれます。
実際に私も任意の自己啓発を研修と同じ扱いで案内した時期がありました。
すると初回参加は集まりましたが、翌月のアンケートで「強制に見える」という記載が増えました。
そこで「任意・推奨・必須」を募集要項に明記したら、問い合わせが減り運用が安定しました。
そこでおすすめなのが「会社主導の研修」と「自己啓発としての研修内容」を紙の上で分けて書いてみることです。
例えば必須のコンプライアンス研修や商品知識研修は前者、キャリア形成やコミュニケーション力向上は後者と整理します。
その上で自己啓発として扱うテーマは「任意」「推奨」「一部必須」など、参加の位置づけをあらかじめ決めましょう。
こうして枠組みを先に整理すれば、具体的な自己啓発の研修内容を考えるときに迷わず、社員への説明もシンプルになります。
自己啓発を企業で仕組みにするなら、評価と強制の境界を先に決めて説明資料に残しておくと安心です。
この準備をしておくと、自己啓発の研修内容に対する社員の受け止め方も変わります。
「会社の都合でやらされている」のではなく「自分のキャリアのために会社が用意してくれた」と感じやすくなるからです。
まずは、現在の研修一覧を書き出し「これは自己啓発として再設計するべきか?」と見直すところから始めてみましょう。
その上で自己啓発の研修内容として扱うテーマだけを抜き出していきます。
そしてこれから紹介するステップに沿って設計していけば、無理のない仕組みに近づいていきます。
自己啓発の研修内容の作り方ステップ
自己啓発の研修内容を具体的に作るときは、三つのステップに分けて考えると整理しやすくなります。
三つのステップとは「目的と対象」「テーマとレベル」「形式と時間」です。
いきなり「どんな講座が良さそうか?」と探し始めてしまうと、現場のニーズと合わないメニューを選んでしまいます。
その結果「結局何が役に立ったのか分からない」というフィードバックになりがちです。
これを避けるためにはステップごとにシンプルな問いを用意して、それに答えていく形で設計していきましょう。
そうすると研修内容に一貫性が生まれ、自己啓発としても続けやすい形になります。
ステップ一つ目は「目的と対象を決める」ことです。
自己啓発を会社へ提出するときの申請の流れも踏まえると、説明が短くても承認されやすくなります。
目的は「この自己啓発の研修内容によって、半年から一年後にどんな変化が起きていれば成功と言えるか」を一行で書きます。
私のクライアントで人事担当の方は、目的を「離職率を下げる」から「1on1実施回数を月2回に増やす」に変えました。
すると研修テーマの選定が1週間で固まり、現場の行動も追いやすくなりました。
ただし指標を細かくしすぎると、形だけこなす人が出るデメリットもあります。
例えば「若手の提案力を高めて受注率を5%上げる」「中堅社員のマネジメント力を底上げにより離職率を下げる」などです。
対象については職種・等級・部署など、誰をメインに想定するのかを絞り込みます。
この段階で目的と対象がはっきりしていれば、研修内容も自然と絞られて参加者も自分事として受け止めやすくなります。
ステップ二つ目は「テーマとレベルを決める」ことです。
同じコミュニケーション研修でも、入門レベルとマネジャー向けでは扱う内容が大きく変わります。
知識中心の講義が良いのか、ロールプレイなどの実践を重視するのかもここで考えます。
ステップ三つ目は「形式と時間・回数を決める」ことです。
短時間の自己啓発ワークショップは、導入テストとして小さく試し、合うテーマだけ広げると費用のムダを減らせます。
集合研修にするのか、自己啓発のeラーニングと組み合わせるのか、何回シリーズにするのかを検討します。
この三つのステップを順番に進めることで「何となく良さそうだから」で選ぶことがなくなります。
そして目的に合った自己啓発の研修内容を組み立てられるようになります。
自己啓発の研修内容とeラーニングの違いと組み合わせ方
最近は自己啓発のeラーニングも一般的になってきています。
すると「研修はすべてオンラインにしてしまえば効率的では?」と感じる人もいるかもしれません。
確かに動画やオンライン教材を使えば、場所や時間に縛られず学べるという大きなメリットがあります。
自己啓発の会社負担にする線引きを事前に決めておくと、受講者間の不公平感と不満を抑えられます。
ただすべてを自己啓発のeラーニングにすると「質問できない」「交流が生まれにくい」といったデメリットも出てきます。
自己啓発のeラーニングだけで完結させる条件を確認すると、集合研修を入れる判断が早くなります。
実際に私も、過去に自己啓発の研修内容をeラーニング中心にした年は受講完了率が上がりました。
ですが1か月後のロープレ実施回数が増えず、対面の練習会を1回入れ直したら改善されました。
ただし対面を増やすと、日程調整と人件費が増えるのがデメリットです。
ここで大切なのは集合研修と自己啓発のeラーニングを対立させるのではなく、それぞれの得意分野を組み合わせることです。
自己啓発の研修内容のうち、知識をインプットする部分はeラーニングと相性が良い場面が多いです。
例えば基本的な理論や手順、事例紹介などは動画やテキストで何度も見返せる形にしておくと、受講者のペースに合わせて学べます。
一方で「練習が必要なスキル」や「価値観の共有」は集合研修の方が効果的です。
ロープレやグループディスカッションを通して「実際の現場でどう使うか」を一緒に考える場を持つことが重要だからです。
すると自己啓発の研修内容が現場の行動に直結しやすくなるので、この役割分担を意識しておくと無理なく設計できます。
具体的には事前学習は自己啓発のeラーニング、当日は対面研修という形がおすすめです。
まずは事前に基本知識をeラーニングで押さえてもらいます。
そしてその後に集合研修で練習をして、自分の職場にどう落とし込むかの議論に時間を使います。
これによって当日の密度が高まり、現場の会話も生まれやすくなります。
自己啓発の研修内容を考えるときは「どこまでをeラーニングに任せ、どこからを対面で行うか」を最初に決めましょう。
そうすれば無駄の少ないプログラムに仕上がります。
自己啓発の研修内容を選ぶためのチェックリスト
最後に自己啓発の研修内容を選ぶときに使える、具体的なチェックリストを紹介します。
研修会社から複数のプログラム提案を受けたり、社内で自己啓発の研修内容案が上がってきたりする機会があります。
外部の自己啓発セミナーを使うときは、目的と現場課題が合うかを事前ヒアリングで確かめましょう。
この時、どれも良さそうに見えて選びきれないという状態になりがちです。
そんなときは感覚だけで決めるのではなく、あらかじめ決めた観点で比較することが大切です。
ここでは、初心者の担当者でも使いやすい五つの観点に絞って整理します。
これらを紙に書き出して比較するだけでも、判断のブレを減らせます。
チェックポイント一つ目は「目的との一致度」です。
事前に決めた目的に対して、この自己啓発の研修内容はどこまで応えているかを確認します。
二つ目は「現場の実務との近さ」で、事例や演習が実際の業務にどれだけ似ているかを見ます。
三つ目は「フォローの仕組み」で、受講後に復習や相談ができる仕組みがあるかどうかです。
四つ目は「時間と負担感」で、繁忙期やシフトへの影響を考えつつ、無理なく参加できるかを判断します。
五つ目は「費用対効果」で、参加人数や期待される成果を踏まえて納得できる金額かどうかを検討します。
この五つの観点で〇、△、×でスコア比較してみると、どの自己啓発の研修内容が自社に合っているかが見えやすくなります。
私のクライアントで総務の方は、提案書を〇△×の比較表にしたことで決裁が約1週間短縮しました。
ところが点数だけで決めると、講師の相性や社内事情を見落とすというデメリットもありました。
そこで最後に講師の説明を短時間だけ試してもらい、現場に合うかを確認してから決めるようにしていました。
また一度決めたら終わりではなく、実施後に必ずアンケートや現場の声を集めましょう。
そして「どこが良かったか」「どこを改善してほしいか」を記録しておきましょう。
これが次回以降の研修内容をブラッシュアップする材料になります。
こうして「決める→実施する→振り返る」のサイクルを回していくことが、研修の質を上げていくコツです。
後は継続していけば、自己啓発の研修内容が少しずつ自社にフィットした形に育っていきます。
編集後記
研修や自己啓発のプログラムを考える立場になると、肩に力が入ってしまうことが多いですよね。
これは「失敗したくない」「選択を間違えたらどうしよう」というプレッシャーを感じることが原因です。
私が現場の担当者と話していて一つ感じることがあります。
それは「最初から完璧なプログラムを作ろうとしない人ほど、長く続く仕組みを育てている」ということです。
まずは小さなテーマで一度試し、受講者の反応を正直に聞き、そこから一つずつ改善していけば十分です。
自己啓発の研修内容も会社と同じように育てていくものだと捉えて、今日決めた一歩を丁寧に歩んでいきましょう。
- 自己啓発の研修内容は目的と対象から設計する
- 自己啓発の研修内容はeラーニングと集合研修を組み合わせる
- 自己啓発の研修内容はチェックリストで比較検討する