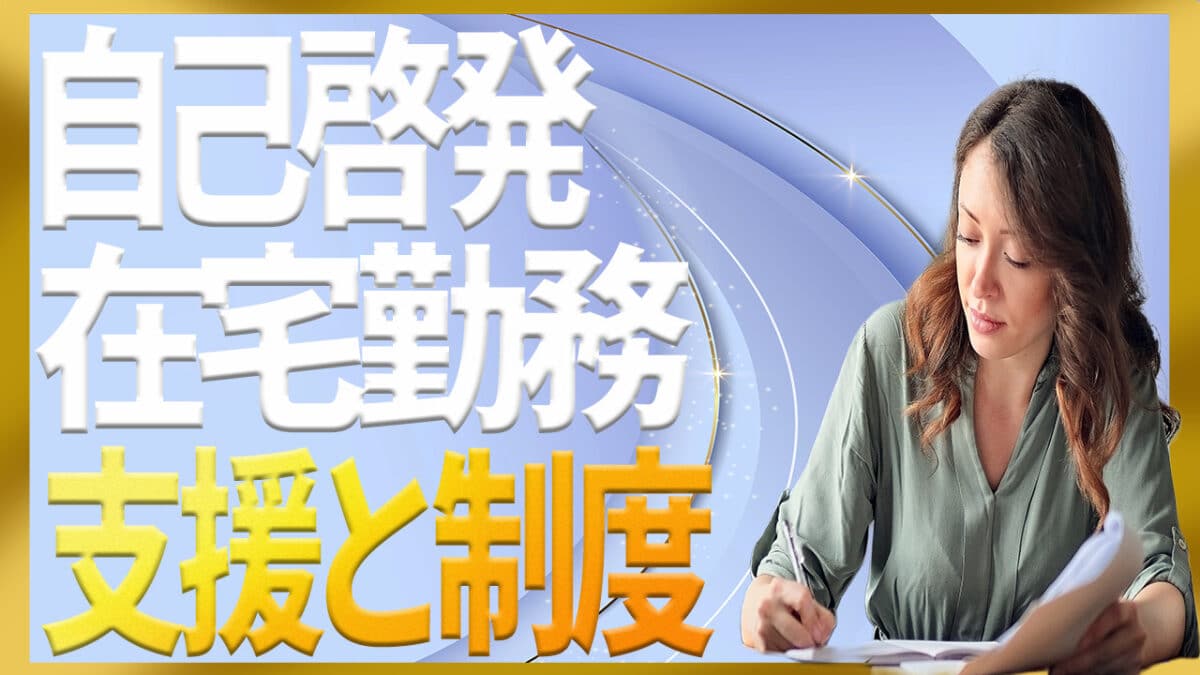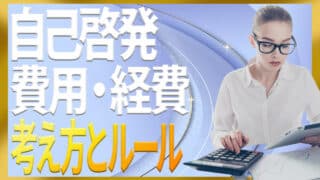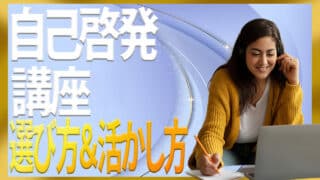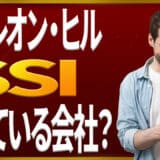自己啓発を在宅勤務で続けられる支援と制度|学習の線引きと運用ルール
今回は在宅勤務で自己啓発を有効活用するコツについて解説します。
・自己啓発って在宅勤務でもできる?
・在宅勤務におすすめな自己啓発を知りたい
こうした疑問や思いをお持ちの人はたくさんいます。
在宅勤務をしながら自己啓発に取り組む人は、会社としての支援や制度を有効活用して自己成長していきます。
一方で「仕事のついで」になり、気づけば数ヶ月何も学べていなかったという人もいます。
そこで今回は在宅勤務で自己啓発に取り組むコツについて解説します。
この動画を見ると在宅勤務での自己啓発を安心して続ける方法が分かりますので、是非最後までご覧ください。
それでは早速、在宅勤務で自己啓発を続ける前提条件から見ていきましょう。
在宅勤務で自己啓発を続ける意義と前提条件
在宅勤務で自己啓発を続ける一番の意義は、働く場所が変わっても自分の成長ペースを自分で守れるようになることです。
通勤がなくなることで時間の余白は生まれますが、その余白は放っておくと家事やスマホにすぐ埋め尽くされます。
在宅勤務での自己啓発をあえて続けると決めることで、今日一日の中で自分のために使う時間が確保されます。
そしてそれを継続することは、将来の選択肢やキャリアの安定にもつながっていきます。
まずは在宅勤務だからこそ自己啓発の時間を意識的に確保する価値がある、と前向きに位置づけてみましょう。
そのうえで前提として大切なのは、体力と生活の土台を崩さないことです。
在宅勤務は仕事とプライベートの境界が曖昧になりやすく、無意識に働きすぎたり、逆に生活リズムが乱れがちです。
睡眠時間が足りず疲れている状態で在宅勤務での自己啓発を上乗せしようとしても、集中力が続かず自己嫌悪だけが残ります。
まずは仕事の時間、休む時間、在宅勤務での自己啓発の時間を大まかに区切り、生活を整えることを優先しましょう。
この方が、長い目で見て成果につながりやすくなります。
例えば在宅勤務の人が「朝の通勤時間がなくなったから、出社時間だった九時までを自己啓発の時間にする」とします。
その場合も睡眠を削って早起きしすぎたり、夜遅くまで残業したりすれば数日で体力の限界が来ます。
そこで大事になってくるのが、自分を守るルールをセットで決めることです。
・23時以降は仕事も学習もしない
・在宅勤務で自己啓発をするのは平日三日だけにする
などメリハリをつけるルールを決めておくと、無理なく自己啓発を続けやすくなります。
実際に私のクライアントも在宅勤務の期間に朝30分の学習を入れたことがあります。
最初の1週間は続いた一方で、2週目に会議が増えると先送りになることが続きました。
そこで火曜と木曜だけに固定して、20分学習+10分間のメモに切り分けてもらうと未実施がほぼゼロになりました。
ただし固定日を増やしすぎると、予定変更のたびに夜へ回して睡眠が削れやすいというデメリットもありました。
在宅勤務で自己啓発を続けるときの土台は、自分の健康と生活リズムを最優先にすると心に決めることだと言えるでしょう。
自己啓発は業務時間か業務外か|残業・サビ残にならない線引き
在宅勤務で自己啓発に取り組むときに整理しておきたいのが、どこまでが業務時間と業務外の学習かという線引きです。
ここが曖昧なままだと、本人は頑張っているつもりでも実質的に自己啓発の残業を抱え込んでしまいます。
これでは、気づかないうちに自己啓発のサビ残になってしまうことがあります。
まず基本の考え方として、以下は労働時間・勤務時間として扱われやすいと押さえておきましょう。
・会社が指示した内容を、会社のために、会社がコントロールできる時間帯に行う学習
逆に以下は、原則として業務時間ではなく業務外の学習とみなされるのが一般的です。
・本人の意思で、自分のキャリアや教養を広げるために行う自己啓発
厚生労働省の通達でも、会社の指揮命令の有無や参加しないことで不利益が出るかが自己啓発と残業の線引きとされています。
つまり形式上は任意の勉強会でも、実態として断れない、参加しないと評価が下がる状態だとします。
これなら、労働時間や残業として扱うべき場面も出てくるということです。
在宅勤務で自己啓発を続けたいなら、以下の区分を本人と会社の両方が同じイメージで共有しておくことが欠かせません。
・業務としての学習
・完全にプライベートな学習
そこで、自己啓発と業務時間の関係をざっくり整理した表を用意しました。
自社の実態に合わせて、労働時間に算入される自己啓発/されない自己啓発の目安としてください。
| 区分 | 労働時間・勤務時間に算入されやすい自己啓発 | 業務外として扱われやすい自己啓発 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 指示された研修・講座 | 上司や会社が参加を指示したオンライン研修、新システムの操作講習など | 案内はされたが完全任意の外部セミナーで、不参加でも評価に影響しないもの | 指揮命令があるか、参加しないと不利益があるかで判断 |
| 必須資格・必須スキル | 業務に必要な資格更新講習、担当業務で必須の法改正セミナーなど | 将来転職など、今の業務と距離のある資格の自己啓発 | 今の職務にどれだけ直結しているかがカギ |
| 在宅勤務中の学習 | 勤務時間内に「学習時間」として予定に組み込まれている自己啓発の業務 | 勤務終了後や休日に、本人の判断で取り組む在宅勤務での自己啓発 | タイムカード・勤怠上どの時間帯に行っているかを明確に |
| 任意参加の勉強会 | 実質的に参加必須で、不参加が評価や配属に影響する勉強会 | 完全に自由参加で、参加有無が査定と切り離されている社内読書会など | 「断りやすさ」と「参加しないことでの不利益」の有無を確認 |
| 自己啓発色の強い活動 | 業務改善プロジェクトの一環として行う読書会やロールプレイ練習 | マインドセットや人生哲学など、職務と直接結びつきにくい一般的な自己啓発 | 仕事の成果指標とどこまで結びついているかで線引きする |
実務では、在宅勤務の画面の向こう側で行われていることは見えづらいです。
そのため何となく学んでおいてと頼んだ自己啓発が、そのままダラダラと自己啓発の残業につながってしまうケースもあります。
こうした事態を防ぐには、自己啓発の業務時間と業務外の時間をカレンダーや勤怠上で分けておくことが重要です。
私のクライアントで在宅勤務チームのマネジャーは、勤怠とカレンダーに業務学習と私的学習を分けて記録ました。
すると勤務時間に算入すべき学習が明確になるという変化がありました。
ただし分類を細かくしすぎると、記録が負担になって運用が止まりやすいというデメリットもありました。
本人としては、これは完全にプライベートな在宅勤務での自己啓発だと思っていたとします。
しかし実態として上司の指示の下で行っているなら、自己啓発の労働時間として扱うべき場面があるかもしれません。
逆に本来は自分のキャリアのための学びなのに、曖昧な雰囲気のまま業務時間にねじ込んでしまうとします。
これでは、周囲からの不信感を招くこともあります。
在宅勤務で自己啓発を長く続けていくためには、これは会社の時間、これは自分の時間という線を自分でも意識しましょう。
そして、必要に応じて上司や人事と相談しながら調整することが大切です。
自己啓発と業務時間の境目を明確にすることが、結果的にサビ残トラブルを防ぎ、安心して学べる土台づくりになります。
在宅勤務で自己啓発を支援する会社の仕組み
在宅勤務での自己啓発を会社として応援したい場合、お金の支援と時間の支援を分けて考えると設計しやすくなります。
対象・上限・申請フローは、自己啓発の制度の具体例を見て社内事情に合わせて詰めると早いです。
お金の支援は書籍購入補助やオンライン講座の受講費補助など、分かりやすい形で在宅勤務の自己啓発を後押しできます。
書籍や講座の補助は、自己啓発の補助の対象と上限を決め、申請を簡単にすると迷いなく回ります。
一方で時間の支援は勤務時間の一部を学習に充てたり、月に一度在宅勤務の自己啓発を共有する時間を設けるなどです。
どちらか一方だけでなく会社の状況と組み合わせることで、社員は安心して在宅勤務で自己啓発に取り組めます。
支援の仕組みを作るときに大切なのは対象、上限、申請方法をシンプルに決めることです。
。在宅勤務での自己啓発に使える書籍購入補助として、年間一万円まで会社が負担
・対象は正社員と一部の契約社員
・申請はオンラインフォームからレシートと簡単な学習目的を提出
こうしてルールを明文化しておけば、社員も遠慮せずに制度を活用できますし、経理や人事も運用しやすくなります。
私のクライアントは書籍補助を年1万円に絞り、申請をレシート+目的一行だけにしたら利用者が増えたそうです。
ただし目的の書き方が曖昧だと差し戻しが起きやすく、最初に具体的な例文を用意するべきだと気付きました。
在宅勤務で自己啓発を支援する仕組みは、難しく作りすぎないことが続けるコツです。
さらに効果を高めるには、学びを共有する場を在宅勤務の中に組み込むことも有効です。
任意学習と研修を混ぜないために、自己啓発の研修の位置づけと扱いも先に整理しておきましょう。
例えば月一回のオンライン朝礼で「在宅勤務での自己啓発で学んだことを共有する時間」を五分だけつくるのも良いです。
オンライン中心にするなら、自己啓発のeラーニングの長所と弱点を押さえて設計の手戻りを減らせます。
あるいは二ヶ月に一度、在宅勤務で自己啓発を実践して成果が出た事例を紹介する、といった小さな取り組みでも構いません。
学びを見える化する場があると、せっかくだから自分も何か続けてみようと思う社員が増えます。
これが継続していくと、在宅勤務での自己啓発が組織の文化として根づいていきます。
支援の仕組みは完璧でなくて良いので、まずは試しに一つ導入してみることから始めてみてください。
在宅勤務で自己啓発を続けるための個人ルール
最後に在宅勤務での自己啓発を続ける上で、持っておきたい小さなルールについて整理しておきます。
どれだけ会社の制度が整っていても、日々の行動を決めるのは自分自身です。
在宅勤務は周りの目が少ないぶん「今日はやめておこう」「明日から本気を出そう」と後回しにしやすいです。
そこで大切なポイントは「何を」「いつ」「どこで」学ぶのかをあらかじめ決めておくことです。
これによって迷う余地を減らすことができ、在宅勤務で自己啓発を続けるための土台になります。
おすすめなのは、次に挙げる三つのルールです。
1,一週間の中で自己啓発デーを決める
2,一回あたりの時間を短く設定する
3,やることリストを細かく分ける
具体的な実例だと次のようになります。
・火曜と木曜の勤務開始前三十分は、在宅勤務での自己啓発に使う
・一回の学習は20分+メモ10分の合計30分だけにする
・やることは『本を一章読む』『動画を一本見る』『メモを三行書く』のように小さく分ける
こうするとハードルが下がり、在宅勤務で自己啓発を「できる日」と「できない日」の差が小さくなります。
すると自然と続くようになり、習慣として定着しやすくなります。
また在宅勤務で自己啓発を続けるなら、家族や同居人とのコミュニケーションも欠かせません。
家の中で仕事と学習を行うため、あらかじめ線引きを、お互いに話し合っておくと良いでしょう。
「この時間だけは話しかけないでほしい」
「ここからは一緒に過ごす時間にしたい」
こうした話し合いを先に行っておけば、後々のお互いのストレスを減らせます。
あとはドアに小さなメモを貼っておく、カレンダーアプリで家族と予定を共有するなど、少しの工夫でも変化が出ます。
在宅勤務で自己啓発の時間を守ることは、家族との時間をおろそかにすることではありません。
これは、メリハリをつけて両方を大切にするための工夫だと捉えてみてください。
編集後記
在宅勤務が広がってから「家にいるのに一日があっという間に終わる」という声をよく耳にするようになりました。
そんな中で自己啓発の時間を確保するのは、決して簡単なことではありません。
それでも週に一度でも「これは自分のための時間だ」と決めて学ぶ人ほど、表情や話し方が柔らかく変わっていきます。
もし在宅勤務で自己啓発の時間を取れていないと感じているなら、まずは一週間のうち30分だけ使ってみましょう。
その時間で、自分のために何かを吸収する時間を予定に入れてみてください。
その小さな一歩が、これからの働き方と心の余裕をじわじわと変えていきます。
- 在宅勤務での自己啓発は生活リズムを整えて土台を作る
- 在宅勤務での自己啓発は業務時間との線引きを先に決める
- 在宅勤務での自己啓発は制度と個人ルールを組み合わせて守る