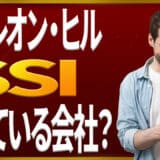自己啓発を趣味として楽しむための3ステップと続けるコツ5選
今回は自己啓発を趣味として楽しむための始め方と続けるコツについて解説します。
・自己啓発に興味はあるけれど、真面目にやろうとすると続かない
・趣味で自己啓発に取り組んだけど、途中で義務感になってしんどくなる
こうした疑問や思いをお持ちの人はたくさんいます。
自己啓発を趣味の一つとしてゆるく続けている人は、楽しみながら自然と知識や行動が増えていきます。
才能ではなく自己啓発を趣味として扱うか、修行のように扱うかの違いを知らずに損をしている人も多いです。
そこで今回は自己啓発を趣味として楽しむためのポイントについて解説します。
この動画を見ると自己啓発を趣味として捉えるメリット、始め方のステップが分かりますので是非最後までご覧ください。
それでは早速、なぜ自己啓発を趣味として考えると続きやすくなるのかから見ていきましょう。
自己啓発を趣味にすると続きやすくなる理由
自己啓発を趣味として捉えると続きやすくなる一番の理由は、結果を急がなくてよくなるからです。
自己啓発を今すぐ人生を変えなければならない道具と考えると、少しうまくいかなかっただけで自分を責めてしまいがちです。
しかし読書や映画、スポーツのように自己啓発も趣味の一つだと考えてみましょう。
そうすれば楽しみながら少しずつ成長できればいい、と肩の力を抜いて続けられるようになります。
結果を急ぐと苦しくなる理由は変わらなければという焦りと、まだ変われていないという比較が常につきまとうからです。
すると本を読むのもノートを書くのも、やらなければならない作業に変わってしまいます。
趣味は本来なら点数をつけるものではなく、やっている時間そのものが心地よいかどうかが大事です。
自己啓発も同じようにやっていて楽しい、続けたいと感じられる形に近づけるほど自然と習慣になっていきます。
イメージしやすいように修行としての自己啓発と、趣味としての自己啓発の違いを表にまとめると次のようになります。
| 観点 | 修行としての自己啓発 | 趣味としての自己啓発 |
|---|---|---|
| 目的 | 早く結果を出すこと | 少しずつ視野を広げて楽しむこと |
| 気持ち | できないと自己否定しやすい | できない日があっても気にしすぎない |
| 続き方 | 一気に頑張って燃え尽きる | 小さく長く続ける |
例えば「毎日絶対に一時間勉強する」と決めると、できなかった日に大きな自己嫌悪が生まれます。
・寝る前の10分だけ自己啓発本を読む
・月に一度だけ自己啓発のイベントに参加する
こうした趣味寄りのルールなら、忙しい日があっても翌日から再開しやすくなります。
自己啓発を趣味として捉え直すことは、自分を追い込みすぎずに成長していくための土台作りだと言えるでしょう。
自己啓発を趣味として始める3つのステップ
自己啓発を趣味として始めるには、次に挙げる三つのステップが役立ちます。
1,テーマを一言で決める
2,時間と場所のルールをゆるく決める
3,最初の一つを決めて小さく始める
いきなりたくさんのことを一度に始めようとすると、趣味ではなくノルマになってしまいます。
最初は驚くほど小さな一歩からで構いません。
なぜこの三つが大事かというと、趣味として続くものは自分で選んでいる感覚とやりやすい環境がそろっているからです。
テーマが曖昧だととりあえず流行っている本を買ってみる、という受け身のスタートになってすぐに飽きてしまいます。
また時間や場所のルールがないと、いつでもできるからと先延ばしになりやすくなります。
そこで自己啓発を趣味として続けるために、最初にシンプルな枠を用意しておくことが大切です。
具体的には次のような流れで始めてみるとスムーズです。
1つ目は、今の自分が一番伸ばしたいテーマを一言で決めることです。
・仕事の段取り力を上げたい
・心を落ち着かせる方法を増やしたい
・人との会話を楽しめるようになりたい
このように一言で表せるテーマを決めておくと、自己啓発のツールや本を選ぶときの軸になります。
2つ目は、趣味の時間にする枠をゆるく決めることです。
・平日の夜、寝る前の10分
・休日の朝、コーヒーを飲みながらの15分
日常の中で無理なく取れる時間と場所を決めることで、自己啓発を趣味として楽しむ自分だけの時間を確保できます。
3つ目は、テーマに合った行動を一つだけ決めることです。
・テーマが仕事なら1冊だけ仕事術の本を選んで1日数ページ読む
・テーマが心なら毎晩3行だけ感謝や気づきをノートに書く
・テーマが人間関係なら、ドラマのセリフや音楽の歌詞から心に響いた一行をメモする
このように自己啓発を趣味として始めるときは、これだけでいいの?と思うくらい小さくスタートするのがコツです。
最初から完璧なメニューを組むのではなく、続けられそうだと感じるレベルまで負担を下げることで趣味としてなじみます。
自己啓発を趣味として楽しめる具体的な例
自己啓発を趣味として楽しむためには、自分に合う遊び方をいくつか持っておくと便利です。
本を読むだけが自己啓発ではありません。
音声や動画で学ぶ、ノートを使って考えを整理する、人と対話する、自分なりの企画を作ってみるなどさまざまな形があります。
いくつかのスタイルを組み合わせることで飽きにくくなり、気分に合わせて楽しめるようになります。
なぜ複数のスタイルが大事かというと、同じ方法だけを続けているとどうしても刺激が薄れてマンネリ化するからです。
例えば本を読むのが苦手な日でも、短いドラマや音楽なら楽しめるかもしれません。
自己啓発の趣味としての具体例を、三つのグループに分けて見ていきましょう。
人と一緒に楽しむ自己啓発のイベント・サークル・ボランティア
一人で本を読むのが飽きるタイプの人には、自己啓発のイベントやサークル、ボランティア活動に参加するのがおすすめです。
人と一緒に学ぶことで刺激が増え、趣味としてのワクワク感も高まりやすくなります。
例えば週末の自己啓発のイベントに参加すると、講師の話以外にグループワークで他の参加者の考え方に触れられます。
これだけで自分だけでは気づかなかった視点が増え、自己啓発を趣味として続けるモチベーションになります。
また、少人数で集まる自己啓発のサークルに参加するのも一つの方法です。
月に一度、気になる本を一冊決めて感想を話し合うだけでも、学びが深まりやすくなります。
サークルの仲間ができると、次の集まりまでにここまで読んでおこうという良い意味での適度なプレッシャーも生まれます。
さらに、自己啓発のボランティア活動という選択肢もあります。
地域でのイベント運営、学びの場を支える側に回ることで、コミュニケーション力や段取り力が自然と鍛えられていきます。
人と関わることが好きな人にとって、自己啓発のボランティアは成長と貢献を同時に味わえる趣味になります。
このように人と一緒に楽しめる自己啓発のイベントやサークル、ボランティアは一人では続きにくい人に心強い選択肢です。
生活と一体化させる自己啓発の音楽・ドラマ・旅行・料理
忙しくて本を読む時間が取れない人は、日常生活と一体化させた自己啓発の音楽やドラマ、旅行、料理がおすすめです。
普段の生活の中に自己啓発のエッセンスを散りばめることで、特別な時間を作らなくても成長のきっかけを増やせます。
例えば、通勤や家事の時間に自己啓発の音楽や音声コンテンツを流しておきます。
すると気分を整えたり、前向きな言葉に触れたりする時間を自然に作れます。
好きなアーティストの歌詞の中に、自分を励ますフレーズを見つけるのも立派な自己啓発です。
また、自己啓発のドラマやドキュメンタリーを見るのも良い方法です。
頑張る登場人物や価値観が揺さぶられるストーリーに触れることで、自分も挑戦してみようという気持ちが生まれます。
ドラマのセリフをノートにメモして、自分へのメッセージとして残すのもおすすめです。
さらに、自己啓発の旅行や料理という視点もあります。
新しい場所を訪れて自分の当たり前が揺さぶられる体験は、それだけで大きな学びになります。
行き先を決めるときに、この旅で身につけたい視点は何かを書き出しておくだけで、旅が自己啓発の旅行に変わります。
日々の料理も、自己啓発の料理として楽しめます。
新しいレシピに挑戦したり、作りながら今日の良かったことを振り返れば、丁寧に生きる練習の時間に変えられます。
音楽やドラマ、旅行、料理といった日常の楽しみの中に、少し自己啓発を混ぜるだけでも、趣味としての学びは育ちます。
気分を上げる自己啓発グッズやツールの活かし方
自己啓発を趣味として続けるうえで、気分を上げてくれる自己啓発グッズやツールをうまく活用するのも効果的です。
お気に入りのノートやペン、アプリなどが一つあるだけで今日も少し書こうかなという気持ちになりやすくなります。
例えば、表紙を見れば前向きになれるノートを一冊用意して、自己啓発のメモだけを書くと決めておきます。
これでそのノート自体がスイッチになります。
ペンも書き心地の良い一本を自己啓発グッズとして選べば、このペンを持ったら自分と向き合う時間意識しやすくなります。
デジタル派の人には、自己啓発のツールとしてスマホアプリを活用する方法もあります。
・習慣管理アプリで読書や日記の時間をチェック
・メモアプリに印象に残った言葉を集めたりする
これだけでも、自分の成長の足跡が見えるようになります。
大切なのは、自己啓発グッズやツールを買い集めること自体を目的にしないことです。
気分を少し上げたり行動に移りやすくする相棒として、お気に入りを決めて長く付き合っていくイメージを持ちましょう。
飽きずに自己啓発の趣味を続けるコツ5選
自己啓発を趣味として続けるには頑張り続ける工夫ではなく、飽きにくくする工夫が大切です。
ここでは無理なく続けるためのコツを五つに絞って紹介します。
どれも特別な才能はいらないものばかりなので、できそうなものから一つずつ試してみてください。
コツが必要な理由はモチベーションが高さに頼っていると、気分が落ちた瞬間に趣味そのものをやめたくなるからです。
どんな趣味でもやる気がある日もあれば、ない日もあるのが普通です。
自己啓発だけを特別扱いせず、他の趣味と同じように波を前提にした仕組みを用意すれば、長期間継続できます。
飽きずに続けるためのコツ5選は、次の通りです。
1つ目は、ハードルを最低ラインまで下げることです。
・1日1ページ読めたらOK
・ノートは1行だけでOK
このように決めておけば、忙しい日でもゼロにしない状態を保ちやすくなります。
2つ目は、完璧にやれなくても自分を責めないルールを決めることです。
週の半分できていれば十分など合格ラインをゆるくしておくと、ちょっとサボっても再開しやすくなります。
3つ目は、月に一度だけ振り返りの時間を取ることです。
ノートやメモを見返しながら「今月はこんなことを考えていたんだな」と眺めるだけでも、自分の変化に気づけます。
自己啓発のサークルに参加しているなら、月に一度だけ感想を共有する時間を作るのもおすすめです。
4つ目は、人に話す場を一つ持つことです。
家族や友人に学びを一つだけシェアする、SNSに感想を一行だけ書くなど誰かに話す機会があると続ける理由が増えます。
興味があれば、自己啓発のイベントやオンラインコミュニティで感想をシェアするのも良い刺激になります。
5つ目は、たまに新しい刺激を入れることです。
いつもは本なら音声講座を聞いてみる、独学ならオンライン勉強会へ参加といった小さな変化を加えれば新鮮さを保てます。
自己啓発を趣味として長く続けるコツは、やる気に頼らない仕組みを作ることです。
すべてを一度に取り入れる必要はありませんが、気になるものを一つずつ試していけば自分に合った続け方が見えてきます。
自己啓発の趣味と現実のバランスをとるポイント
最後に大切なのは、自己啓発の趣味と現実の生活とのバランスをとることです。
自己啓発に熱心になるほど「もっと学ばなければ」「もっと成長しなければ」と自分を追い込みやすくなります。
しかし趣味としての自己啓発が行き過ぎると疲れてしまい、本来の仕事や人間関係に支障が出てしまうこともあります。
そうならないためにも、ここまでやれば十分という自分なりのラインを決めておくことが大切です。
なぜバランスが重要かというと、自己啓発は人生を豊かにするための手段であって人生そのものではないからです。
成長したい気持ちはとても大切ですが、休む時間や遊ぶ時間、何もしない時間も同じように大切です。
自己啓発に時間とお金を使いすぎると、いつの間にか不安の方が大きくなります。
そして「こんなにやっているのにまだ足りない」と自分を責めるループにはまりやすくなります。
バランスをとるためのポイントを整理すると、次のようになります。
まず自己啓発に使う時間とお金の上限をざっくり決めることです。
・平日は1日30分まで
・自己啓発関連の出費は月◯円まで
このようにあらかじめ決めておけば、やり過ぎを防げます。
次に自己啓発以外の楽しみも意識して残すことです。
散歩や趣味の時間、人との雑談など成長とは直接関係なさそうな時間こそ、心の余裕を作ってくれます。
最後に今の自分にとって大切な優先順位を書き出すことです。
仕事、家族、健康、趣味などを書き出して眺めてみると、自己啓発がその中の一つであることを客観的に確認できます。
このように自己啓発を趣味として楽しむときは、やることだけでなくどこで緩めるかもセットで考えましょう。
自分の生活全体を大切にしながら無理のないペースで続けていくことで、自己啓発は心強い味方になってくれます。
編集後記
自己啓発に真面目に取り組む人ほど、楽しむより頑張るが先立ち途中で息切れしてしまうケースを多く見てきました。
相談を受ける中で感じるのは、変わりたい気持ちが強い人ほど自分に厳しすぎるということです。
そこでおすすめしているのが、自己啓発の時間を人生の中の一つの趣味としてカレンダーに入れてしまう方法です。
例えば週に一度だけ「自己啓発カフェタイム」と予定を入れ、その時間は本やノートを片手にのんびり過ごしてもらいます。
多くの人が頑張る自己啓発から味わう自己啓発に切り替えたとき、表情が少し柔らかくなりました。
そして結果的に行動も続きやすくなっていました。
もし自己啓発に疲れを感じているなら、一度立ち止まって趣味としての距離感を試してみてください。
- 自己啓発を趣味として小さく楽しく続ける
- 自己啓発を趣味として自分に合う遊び方を持つ
- 自己啓発を趣味として生活全体とのバランスをとる