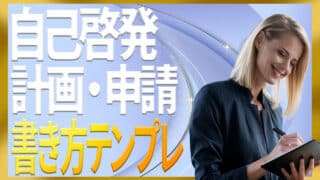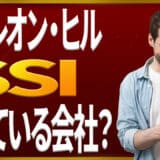自己啓発の評価の仕方|OKRとチェックリストで成長を見える化する
今回は自己啓発を評価によって成長につなげるコツについて解説します。
・自己啓発を評価から取り組みを成果に変えるには?
・自己啓発に取り組む社員の評価基準を決めたい
こうした疑問や思いをお持ちの人はたくさんいます。
感覚だけでほめたり叱ったりしていると、本人も感覚的になってせっかくの努力が長続きしません。
かといって数字だけを追いかける評価だと、自己啓発がノルマになって学びの楽しさが失われてしまいます。
そこで今回は社員が頑張りたくなる自己啓発の評価について解説します。
この動画を見ると自己啓発の評価をOKRとチェックリストで見える化する方法が分かりますので、是非最後までご覧ください。
それでは早速、自己啓発の評価を通じて何を見たいのかを整理するところから見ていきましょう。
自己啓発の評価をする意味と基本の考え方
自己啓発の評価を考えるときに最初に押さえる点は、評価はテストではなく成長の確認と応援のために行うことです。
点数をつけることが目的になると、社員は評価のたびに緊張して減点されないための自己啓発になってしまいます。
そうではなく次に挙げる二点を対話の材料として自己啓発の評価を使うと、本人も前向きに受け止めやすくなります。
1,この一年でどんな変化があったのか
2,何がうまくいってどこを一緒に改善したいのか
こうして評価の目的を最初に共有しておくことが、後のすれ違いを防ぐ第一歩にもつながります。
制度設計の前に自己啓発の制度の全体像を押さえると、社内の判断が揃って後から揉めにくいです。
次に自己啓発の評価では、頑張りと結果の両方を見る視点が必要です。
結果だけを見ると外部環境に左右されやすい職種ほど不利になります。
また頑張りだけを見ると成果とのつながりが見えず、周囲の納得感が下がります。
ですので次に挙げる三つの層に分けて整理すると、バランスよく評価できます。
1,どのくらい行動したか
2,行動の質がどう変わったか
3,仕事の結果にどのような影響が出たか
こうして分けておくと、結果がまだ出ていない段階でも「ここまでは前進できている」と本人に伝えやすくなります。
実際に私も自己啓発の評価を結果だけで見ていた時期は、数字が動かない人ほど意欲が下がりやすい点に悩みました。
そこで行動量と行動の質も一緒に確認する形へ変えてみました。
すると1か月後には、面談で本人が次の一手を具体的に言えるようになる割合が増えました。
例えば営業職の社員が「毎月一冊ビジネス書を読んで要約を提出する」という自己啓発に取り組んだとします。
行動の量としては読書冊数や提出回数で確認できますが、それだけでは仕事とのつながりが分かりません。
そこで資料の明確さや商談での質問の質など、質に目を向けて上司や同僚からのフィードバックも含めて変化を確認します。
さらに一定期間が経過したら、受注率や顧客からの評価コメントを見て、仕事の結果との関係を話し合います。
こうすれば自己啓発の評価が単なる感想ではなく、納得につながる対話へと変わります。
評価を具体化するには、自己啓発が仕事でどう表れるかの例を社内で集めると基準が作りやすいです。
OKRを使った自己啓発の評価の枠組み
OKRとは「大きな目標(Objective)」と「達成度を測る鍵の結果(Key Results)」をセットで決めるシンプルな仕組みです。
自己啓発の評価にOKRを取り入れるときは「目指す人物像」「具体的な働き方」といった質的な目標をOとして書き出します。
その上で行動、スキル、結果の三つの観点からKRを決めていきます。
重要なのは完璧な指標ではなく「これなら半年後に一緒に振り返れそうだ」と感じるレベルで十分だと割り切ることです。
あとはやりながら少しずつ調整していけば問題ありません。
自己啓発の評価に使えるOKRの例として、若手社員の自己成長を応援するケースを考えてみましょう。
まずObjectiveを「自分で考えて動ける若手社員になる」と設定するとします。
OKRの土台として、自己啓発を会社の目標と結びつける考え方も確認しておくと設計が楽になります。
次にKey Resultsとして以下の項目を決めました。
・月に一回、新しい提案を一件以上出す
・週に一度、先輩や上司に質問や相談をする
・四半期に一つ、自分で決めた課題図書を読んで学びを共有する
これなら行動したかどうかが分かりやすく、上司との面談でも具体的な振り返りがしやすくなります。
評価と連動させるなら、自己啓発の研修の位置づけも先に明確にしておくと受講者が迷いにくいです。
上記のケースのように、KRは3〜5個程度に絞ると追いかけやすくなります。
私のクライアントで最初にKRを7個にしたところ、2週間で更新が止まって運用が形だけになる状況が発生しました。
そこでKRを3個に絞り、週1の5分チェックを定着させてもらうようにしました。
すると翌月から記録が続きやすくなり、本人の自己評価も具体的になりました。
OKRを活用すれば、自己啓発の評価が「なんとなく成長した気がする」という曖昧な印象から変わります。
具体的には「ここまでできている」「ここから先を一緒に考えよう」という対話になります。
Oは少し背伸びした理想像、KRは現実的に追える行動や変化と意識して分けると良いでしょう。
すると本人も無理のないペースで取り組めます。
設定が完了して行動段階に入ったら、半年や一年ごとにOKRを見直す習慣を作りましょう。
そこで「続けるKR」「卒業するKR」「新しく追加するKR」を一緒に決めていくようにします。
こうすれば自己啓発の評価は、自然と成長の記録にもなっていきます。
自己啓発の評価に使えるチェックリスト例
OKRで大枠の方向性が決まったら、次は日々の面談や期末の振り返りにそのまま使えるチェックリストを用意しましょう。
自己啓発の評価は土台がないと担当者の負担が大きくなり「忙しいから今回は見送りで」と形骸化しがちです。
しかし事前に共通のチェック項目を決めておけば、本人と上司のどちらも同じ観点で進捗を確認できます。
チェックリストは難しく考えず「行動」「変化」「仕事への影響」の三つを、一行ずつ問う形にするとシンプルです。
評価の説明資料は、自己啓発の会社への提出文の型に寄せると差し戻しが減り、承認が早まります。
実際に私もチェック項目を増やして精度を上げようとしたことがあります。
ただしこれは書き込みの負担が増えて、面談時間が伸びるというデメリットがありました。
そこで項目を3問に戻してコメント欄を一つにしたら、3か月後には記録が途切れずに振り返りの質も上がりました。
使い方:自己啓発の面談や評価シートにそのまま転記して、〇やコメントを書き込んでください。
| 項目 | 質問の例 |
|---|---|
| 行動は続いたか | 予定していた行動(学習・実践・振り返り)はどの程度続けられましたか。 |
| 変化はあったか | 考え方や習慣、人との関わり方に、本人が実感できる変化はありましたか。 |
| 仕事への影響 | 業務の質やスピード、周囲からの評価などに、プラスの変化は表れていますか。 |
このチェックリストを使うときは、すべてを完璧に〇にすることをゴールにしないことが大切です。
自己啓発の評価は未達成を責めるためではなく「どこまで来ているか」「次に何を工夫するか」を一緒に探すツールです。
ですので面談では〇と×だけで終わらせず「続けられた理由」「止まってしまった理由」を丁寧に聞くようにしましょう。
そして本人が自分で気づきを言語化できるように、支援してあげることが大切です。
そうすることでチェックリスト自体が、次の行動を決めるための対話のきっかけになります。
指標が固まりにくい場合は、自己啓発の事例を集めて共通項から評価項目を作ると検討が進みます。
自己啓発の評価を本人と共有するときのポイント
自己啓発の評価がうまく機能するかどうかは、本人への伝え方に大きく左右されます。
同じ内容でも伝え方次第で「応援されている」と感じるか「責められている」と感じるかが変わってしまうからです。
評価面談ではいきなり不足点の追求ではなく「できていること」「続けられていること」から順番に確認するのが基本です。
そこから改善したい点がある場合は、ダメ出しではなく一緒に工夫したいポイントとして扱いましょう。
そして具体的な次の一歩を相談する形にすると、本人も前向きに受け止めやすくなります。
自己啓発の評価を共有するときの流れとしては、次の三段階にするとスムーズです。
1,本人の自己評価
2,上司からのフィードバック
3,次のOKRと行動のすり合わせ
まずはOKRとチェックリストを見ながら、自分なりの手応えや課題を本人から話してもらいます。
その後で上司が見ていた変化や成果を伝え、認識のズレがないかを確認します。
最後に「次の期間はどこに力を入れるか」「どのKRを調整するか」を一緒に決めます。
この流れを毎回繰り返すことで、自己啓発の評価は単発のイベントではなく継続的な対話の場になっていきます。
例えば「学びのアウトプットが少ない」と感じている社員がいるとします。
その社員に対して「もっと頑張りましょう」と伝えても、本人は何を変えれば良いのか分からず落ち込んでしまいます。
一方で「月に一回の学び共有会で、あなたの発表回数を増やしてみるのはどうでしょう」と具体的な提案をしてみます。
前者よりも後者の方が、次に取るべき行動がはっきりするのは明確ですよね。
このように自己啓発の評価は指摘で終わらせず、一緒に作戦会議をする場としてデザインすることが重要です。
それが相手との信頼関係を守りながら成長を促すポイントになります。
自己啓発の評価でメンタルを傷つけないための注意点
最後に自己啓発の評価を行う上で、メンタル面のケアについても触れておきます。
自己啓発は本人の価値観や、将来の不安に深く関わるテーマです。
ですので評価の仕方によっては「自分そのものを否定された」と感じさせてしまう危険もあります。
特に真面目な人ほど「もっとできたはずなのに」と自分を追い込みやすく、評価の場がプレッシャーになってしまいます。
だからこそ人としての価値と、今の成果や行動はきちんと分けて伝える姿勢が欠かせません。
評価はあくまで行動や結果に対するフィードバックだと、繰り返し言葉にして相手へと伝えましょう。
自己啓発の評価でメンタルを守るためには、比較の軸を工夫することも重要です。
他の社員と比較してばかりいると「自分は劣っている」という感覚が強くなり、自己啓発への意欲そのものが下がります。
そこで過去の自分との比較を軸にし「一年前と比べてどうか」「三ヶ月前とどこが変わったか」を一緒に確認します。
私のクライアントで他者比較の言い回しが評価コメントに混じると、翌月の自己啓発の行動数が落ちる人がいました。
そこで比較軸を過去の自分に戻してもらい、できた点→次の工夫の順で話す形に変えてもらいました。
すると翌四半期には、面談後の行動が安定するようになりました。
またすべてのKRが達成できていなくても、重く捉える必要はありません。
「ここまではできている」「まだ途中だが方向性としては良い」といった細かな前進を拾い上げることも大切です。
こうした小さな変化を一緒に喜ぶ姿勢が、安心感につながります。
さらに自己啓発の評価の場が終わった後に「やってよかった」と感じてもらえるようにすることも大事です。
そのためには、面談の最後に「今日の対話の印象」「明日から試すこと」を本人の言葉でまとめてもらうと良いでしょう。
こうして評価を裁定ではなく、次の一歩を決める場に変える工夫をしてあげましょう。
すると自己啓発の評価はメンタルを消耗させるものではなく、むしろ心の支えになっていきます。
評価の仕組みだけでなく、こうした関わり方の工夫もセットで見直していきましょう。
編集後記
自己啓発の評価を考える場面では「ちゃんと制度を作らなければ」と力が入りがちですよね。
すると相手の事を考えるよりも、複雑な仕組みを求めてしまいがちです。
ですが現場で長く回り続けているのは、シンプルで使う人の顔が思い浮かぶ仕組みです。
私が多くの組織の話を聞いてきて実感しているのは、完璧な指標よりも対話のための共通言語があるかどうかです。
なぜならその方が、結果的に社員の成長につながっているからです。
今回紹介したOKRとチェックリストの考え方を、自社の文化やサイズに合わせて少しずつ試してみましょう。
その中から自社にふさわしい、自己啓発の評価の形を一緒に育てていってみてください。
- 自己啓発の評価は成長を確認し応援するために行う
- 自己啓発の評価はOKRとチェックリストで整理する
- 自己啓発の評価は対話を通じてメンタルも守る